健康・病気 2022年3月21日

イヌの耳はとってもデリケート🥲
犬の場合、家での耳そうじはほとんど必要ありません。
犬の耳には自浄作用が備わっているのです🌿
犬の耳はデリケートな造りになっており、
乱暴な手入れは厳禁です😵💫
ただし、耳が汚れやすい子や外耳炎などにかかっている子については、ケアが必要です。
犬の耳掃除の適切な頻度や、犬が嫌がらない理想的なケア方法について解説します。
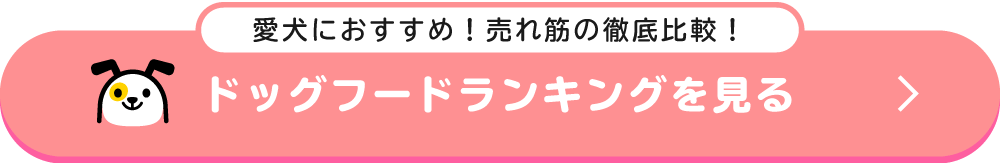

そもそも犬の耳掃除はした方がいいのでしょうか。
実は、外耳炎などのトラブルがなければ、基本的には耳掃除は必要ありません。
これは、本来耳には奥でできた耳垢を手前から外に出す『自浄作用』が備わっているからです。
逆に、耳の本来持っている自浄作用を阻害してしまうような間違った耳の洗浄をしてしまうと、
外耳炎の原因になってしまうことがあります。
なので、無理に耳の中を掃除して、耳垢を全部とりきるというのではなく、
自浄作用によって出てきた見える範囲の汚れを優しく拭き取るくらいのケアがよいでしょう。

耳の中に汚れがある時には、その量に注目してみましょう。
量が少なく、耳の中に赤みや痒みがなければ、
それは自然と出てきた耳垢なので、優しくコットンなどで拭き取ってあげましょう。
耳垢の量が多い、もしくは耳の中が赤い、
痒がったりする時には、外耳炎を起こしているかもしれません。
特に黒い耳垢が多い時には、耳ダニという目には見えない
小さなダニが寄生している可能性もあるので、病院でしっかりと診てもらいましょう。

チワワなど立ち耳の犬種は、
外耳道の通気性がよいため蒸れにくく、それほど外耳炎の心配はありません。
トイ・プードル、ミニチュア・ダックスフンド、シー・ズー、ゴールデン・レトリーバーなどの垂れ耳の犬種は、外耳道に空気が通りません。
そのため、茶色い耳垢が増えていないか、耳が臭くないか、
耳の皮膚が赤味を帯びていないかなどをこまめにチェックするとともに、耳が汚れていたら月1~2回ほど耳掃除をしてあげましょう。
立ち耳でも、フレンチ・ブルドッグは脂漏体質のため、外耳炎になりやすい犬種。
このように外耳炎の好発犬種もこまめに観察し、耳がベトついていたり耳垢が溜まっていたら耳掃除をしてあげてください。
その他にも、たれ耳の犬種も
耳が汚れやすいので、定期的にチェックしましょう。
上記の犬種に限らず、耳垢がたくさん見られるときには、
一度動物病院で耳の中の様子や耳垢の状態を見てもらい、耳掃除について相談するといいでしょう。

耳そうじをするかどうかはともかく、耳のチェックは欠かさないようにしてください。
汚れていないか、赤くなっていないか、かゆがっていないか、
悪臭がしないかを確認して異常があれば動物病院で診てもらいましょう。

犬の耳そうじは、基本的には自浄作用になります。
自浄作用によって出てきた汚れをきれいにして
外で遊んでついた土ぼこりを取るくらいで十分です😊

デリケートな犬の耳に綿棒や乾いた布は耳をきずつけてしまうのでやめましょう🙅♀️
専用のローションやクリーナーをつけたコットンを使ってください。
コットンをお湯やイヤークリーナーで湿らせ、
見える範囲の汚れを優しく拭き取りましょう。

力を入れてこすると、炎症を起こすことがあります。
優しく”ふきとる”感覚で、汚れを落としてあげてください。

専用のローションなどをつけたコットンを使ってそっと汚れをふきとります。
耳を傷つけたり、汚れを奥にいれ無いように注意してください。
耳の異常があるか毎日確認します。
炎症を起こしてるか、かゆがっていないか、
悪臭がしないかなとチェックしてください✏️

耳掃除をしようとすると飼い主さんの手にかみつくなど、
愛犬が耳掃除を嫌がる場合は、まずは耳を触られるのに慣らすことから始めましょう。
すぐに食べきれない硬めのジャーキーなどを愛犬にかじらせながら、
耳を触られることに対するネガティブなイメージを消すようにします。
そのレッスンを続けるうちに、耳掃除ができるようになる犬も少なくありません。
もしイヤークリーナーや耳掃除シートに対する苦手意識が完全にぬぐえない場合は、
おやつをかじらせながら耳に意識がいかないようにしてケアをするとよいでしょう。
飼い主さんが緊張していると、そのテンションを感じ取って愛犬も緊張したり警戒したりしがち。
飼い主さんがまずは落ち着いて、笑顔で愛犬に接しながら耳掃除をするのも重要なポイントです。
おやつを使用しての耳掃除も困難な場合は、トリミングサロンや動物病院に耳掃除を依頼するのが最良の対処法と言えます。
なお、そもそも愛犬が外耳炎にかかっていて痛みがあると、飼い主さんに耳を触られるのを嫌がるはずです。 その疑いがあるようなら、早めに獣医師に診てもらってください。

犬の耳には自浄作用があり、耳の皮膚にはバリア機能が備わっています。
耳掃除をしすぎると、皮膚のバリア機能が損なわれる危険性があるので要注意。
特に、綿棒を使用しての耳掃除は、デリケートな外耳道の皮膚を傷つけたり、
せっかくの自浄作用で外に出てきた汚れを耳の奥に押し戻してしまう恐れがあるので、禁物です。
耳かきも、耳を傷つけるので絶対に使用してはいけません。
人間と違って顔をブルブルと高速で振ることができる犬たちは、耳の内部の液体を外に排出できますが、
老犬や幼齢の子犬や病中病後などで顔を振ることができない場合は、
イヤークリーナーを注入しての耳掃除はやめておきましょう。
炎犬の耳の病気で多いのは外耳炎になります。
耳垢の量が増えたり、耳の中があかくなったりすると、外耳炎が疑われます。
犬が頻繁にかゆがっているのも外耳炎の症状です😖病院で診てもらいましょう🏥
 キーワード一覧
キーワード一覧