しぐさ・生態 2023.01.12

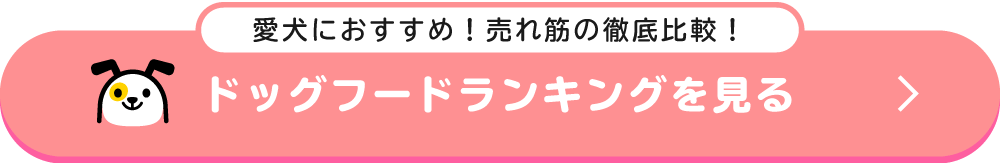

重要な項目からチェックしてみてください!

顔をよく見て、目やにが多くないか、
耳の中が汚れていて耳アカがないかなど
チェックしましよう。
また、身体全体を見て、
被毛に変色している部分があったり、
毛が少なくなっていたりすることは、
清潔に育っていない可能性もあります。

やさしく抱き上げてみたときに、
緊張のあまり硬直したり、
手足をバタバタさせたりしないかチェック。
こうした状態がすぐに収まればとくに問題はありません。

生まれつき腸が丈夫でなく、
飼育環境の悪さから感染などにより
軟便や下痢をしている子犬がいます。
ただれていたりせず、きれいかどうか
チェックしましょう。

子犬は通常、好寄心旺盛で活発です。
呼んだときに駆け寄ってくるか
どうかチェックしましょう、
反応がない場合は、体調が悪いか
人間を怖がっているのかもしれません。

同じ場所を回り続けたり、
身体の同じ場所をなめ続けたりといった
常同行動が見られないかチェック。
こうした行動があるわんこは、
何らかの不安やストレスを抱えています。

100%健康なわんこを迎えられるとは限りません。
ここで紹介するのは、できるだけリスクを低くするためのチェックポイントとなります。
順位が高いほど重要度も高くなりますので、
参考にしてください。
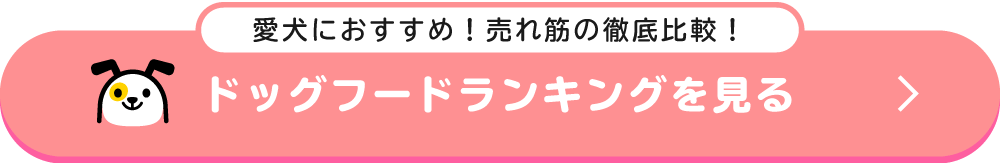
重要な項目からチェックしてみてください!

オスのマーキングは去勢等(時期やしつけの影響もある)で防げる可能性もありますが、
そのリスクを避けるためメスを選ぶ人もいます。
メスには年1〜2回ヒートがあり、
その間はおむつが必要に。
避妊手術をすればなくなりますが、
「メスの避妊手術のほうが負担が大きいから」と
オスを選ぶ人もいます。

やんちゃで甘えん坊です!
多くの犬種でオスはメスに比べて大きくなります。
大型犬の場合はとくに筋肉質で力が強くなるため、
大人になってからも
お世話ができるかを考えてみたほうが良いでしょう。
オスの魅力はやんちゃで甘えん坊なところ。
成長しても甘えてほしい人に向いています。

顔つきも性格もやさしい
個体差はありますが、メスはオスにくらべると
落ち着いていてやさしい傾向があります。
顔つきもやさしく遊ぶときもオスほど激しくないため、
中には初心者向きという意見も。
また、可愛い洋服でおしゃれをさせたくて
メスを選ぶ人もいるようです。

一般的には、オスよりもやさしくて
落ち着いているメスの方が初心者向きといわれています。
しかし、個体差があってメスでも気が強いわんこもいるため、一概にはいえません。

めくって、ニオイをたしかめ、耳の中を覗いてみましょう。
耳の中が汚れていないか異臭がしないか確認。
黒い耳アカがあったら耳ダニの可能性もあります。
犬にかゆがる様子がなく少しニオイがする、少しの耳アカ程度ならば、
洗浄液を使って犬の耳をキレイにして観察しましょう。
洗浄すれば菌の繁殖を押さえて、外耳炎の予防になります。
しかし下記のような状態は、すでに外耳炎、もしくは他の耳の病気になっている可能性があるので、獣医師の診察を受けてください。
目が赤いと結膜炎を起こしている場合があります。
多量の目やには、感染症のサインの可能性も。
目ヤニは、起きた後に少し出る程度ならば正常です。
健康な状態でも、ほこりやまつげなどが目に入って一時的に涙が出て、目ヤニが多く出る場合がありますが、
その時は目薬(犬猫用目薬、または、人間用の防腐剤等の含まれていない人工涙液タイプの目薬)で洗い流して、
丁寧に涙をふいて様子をみてください。
しかし、下記のような状態は、結膜炎、角膜炎、流涙症(りゅうるいしょう)などに
なっている可能性があるので、獣医師に診てもらいましょう。
歯の咬み合わせも非常に大切になります。
下顎が小さいことは全ての犬種で欠点です。
口から少しニオイがする、歯垢がついている程度の状態なら、
歯磨きを行うことで、口の中の状態を健康に保ち、歯周病を防ぐことができます。
まずは、愛犬を慣らして、毎日歯磨きするのがオススメです。
しかし、しっかりと歯石がついていたり、不快なニオイがある場合は、
歯周病になっている可能性があります。
また、歯茎が赤い場合は、歯肉炎、口内炎や腫瘍なども考えられるので、
早めに動物病院で診てもらいましょう。
また、歯石などがないのに、口から異臭がする場合は、肝臓や腎臓に異常も考えられます。
適度に湿っていればOKですが、
鼻水や鼻の周りが汚れている場合は
何かに感染している可能性も。
咳やくしゃみがでていないか、呼吸は正常かなど落ち着いている状態で様子をみましょう。
くしゃみや咳なども単発性のもので、その後元気に過ごし食欲もあるのなら、そのまま様子を観察しましょう。
しかし、くしゃみを繰り返す、頻繁に咳をする、たくさん鼻水が出ている場合は、感染性の疾患や、呼吸器系の疾患、アレルギー、鼻腔内異物、腫瘍、歯の疾患など、
さまざまな病気が考えられるので、獣医師に診てもらいましょう。また、心臓病などで咳が出ることもあります。
人間の風邪に似た症状ですが、犬ジステンパーや犬伝染性気管・気管支炎(ケンネル・コフ)の場合、放置していると死に至る危険もあります。どちらも、混合ワクチンの接種で予防できるので、年1回の接種をオススメします。
運動など、激しく体を動かした後に、息があがるのは当然です。
口をあけて、ハァハァするのは、水分の蒸発と放熱を行っているからで、水分補給をして、
しばらくすると落ち着くのが一般的です。
しかし、熱中症などの場合は、すぐに対策が必要ですし、思い当たる節がないのに息が荒い、
舌や唇の色がおかしい、ヒューヒューゼーゼーなどの呼吸の音が聞こえる場合は、何らかの病気が疑われます。
体全体をやさしくなでながら、腫れやしこり、イボなどがないかチェックしましょう。
おなかが膨れていても、明らかな食べ過ぎの場合は、一時的なもので、時間がたてば元にもどります。
しかし、それ以外の場合は病気のサインかもしれません。おなかが膨らむ原因には、臓器そのものが大きくなっている場合があり、胃拡張胃捻転症候群(いかくちょういねんてんしょうこうぐん)や腹腔内腫瘍(ふくくうないしゅよう)、雌の場合は子宮蓄膿症(しきゅうちくのうしょう)や子宮水腫(しきゅうすいしゅ)の可能性も考えられます。
また、循環器疾患、泌尿器疾患や、肝疾患などで腹水が溜まっていたりすることもありますので、安易に考えず早めに動物病院で診てもらいましょう。
犬も高齢になると皮膚腫瘍ができやすくなります。
特に乳腺にしこりがある場合は、乳腺腫瘍が疑われます。雌だけでなくまれに雄にも発生する病気なので、雄でも注意してください。
また、ホクロやイボに見えるものの中には、マダニの吸着もあります。マダニは犬の体に吸着すると小豆大になり、 無理やり取ると牙が残って炎症を起こす原因になるので、動物病院で除去してもらいましょう。
さらに、マダニの場合は、犬の命に関わるバベシアと言う病気を媒介しますので、注意が必要です。 新たなイボやホクロのようなものを見かけた場合も、念のため獣医師に診てもらうと安心です。
普段は触っていても平気なのに、ある日突然、その場所を触ると逃げたり、怒るなど、嫌がるしぐさやいつもと違う反応を見せたのなら、その場所に痛みがあるかもしれません。
まずは、外傷や腫れなどがないか確認しましょう。目に見えない場合でも、打撲などの怪我や関節炎、椎間板の病気、さらに内臓の病気も疑われます。
特に背中を丸めて、じっとしていることが多い場合は、背骨や腹腔内に痛みがある可能性が高いので、速やかに動物病院で診察を受けましょう。
毛づやがない場合は栄養不足、
脱毛はストレスで同じ場所をなめているか
皮膚病の可能性があります。
掻くことが多いなど、かゆみを伴うしぐさを多くする場合は、ノミやダニなどの外部寄生虫の感染が疑われます。
毛を開いて、黒いゴマのようなものがついている場合、それがノミの糞である可能性も。
黒色の耳アカが多い場合は、耳ダニによる外耳炎かもしれません。
また、疥癬や毛包虫と言われるダニや、細菌や真菌などの感染、アレルギーなど、
ひどいかゆみを伴う皮膚病もあり、犬が爪を立てて掻くことにより、さらに皮膚を傷つけ、悪化する場合があります。
毎日の便の回数や状態、尿の回数や量、色をチェックしましょう。
下痢や軟便だからといって、病気とは限りません。
牛乳を飲んで下痢をする犬もいますし、フードを急に切り替えた時や、アレルギーやストレスで下痢をする場合もあります。
しかし、体力のない子犬や高齢犬の急性の下痢が悪化した場合、死亡することもあるのであなどらないでください。
子犬や高齢犬の下痢は、早めに診察を受けましょう。元気があり活発で食欲もある成犬の一時的な下痢や軟便は、
多くの場合ゴミ箱をあさったり、何かおかしなものを食べたり、飲んだりした場合も多いので、少し様子を観察して判断してください。
ただし、続く場合や他の症状がある時は、獣医師に診てもらいましょう。
また、慢性的な軟便で、痩せてくるような場合も動物病院での診察は不可欠です。
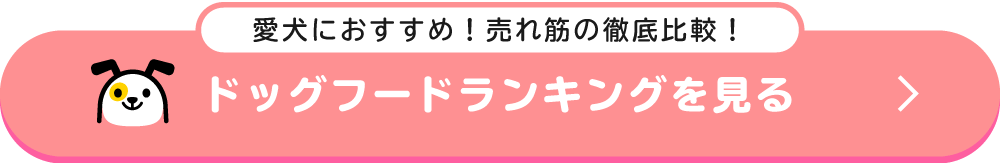

生まれつき身体の弱いわんこの場合、
一生通院が必要になる場合もあります。
家族として迎えたわんことは、
幸せに暮らしながら生涯をともにしたいもの。
そのためには、健康状態や性質を確認して選ぶことが大切です。
健康状態はわんこの行動やしぐさに現れます。
そのサインや、オスとメスとの身体の違いなどを知っておけば、選ぶ際の目安になるでしょう。
「目やにが多くないか」といった見た目のチェックだけでなく、身体にさわったりできれば一緒に遊びながら、
しぐさや行動を見てチェックすることも重要です。
ただし、分かりづらい病気などもあるため、
獣医師の健康チェックをクリアしているほうが良いでしょう。
一般の人が見ただけでは分からない
先天性の疾患もあります
初めてわんこを迎える人には犬の健康状態は、
なかなか分かりづらいもの。
そのため、獣医師の健康チェックをクリアしていることが
最低条件となります。子犬を購入する際は、
獣医師による健康診断書をもらうようにしましょう。
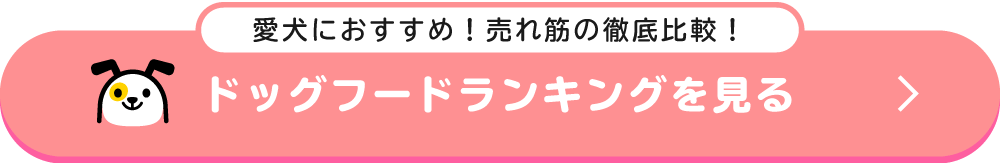
 キーワード一覧
キーワード一覧飼い主さんたちの関心が高まっている最新のアイテムやノウハウを厳選。話題のドッグフード、便利なお出かけグッズなど、今読むべき記事をチェック!
すべての記事を見るFor Happy,
Healthy Dogs.